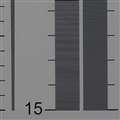OLYMPUS OM-D E-M1 �{�f�B
�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� ���i���ڃO���t
- �t�������Y

-
- �f�W�^�����J���� -��
- �~���[���X��� -��
OLYMPUS OM-D E-M1 �{�f�B �̌�ɔ������ꂽ���i
OLYMPUS OM-D E-M1 �{�f�B�I�����p�X
�ň����i(�ō�)�F�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� [�u���b�N] �������F2013�N10��11��
OLYMPUS OM-D E-M1 �{�f�B�@�̃��[�U�[���r���[�E�]��
| �]������ | ���[���� | �J�e�S������ | ���ڕʃ����L���O |
|---|---|---|---|
| �f�U�C�� |
4.68 | 4.52 | -�� |
| �掿 |
4.42 | 4.53 | -�� |
| ���쐫 |
4.37 | 4.27 | -�� |
| �o�b�e���[ |
3.51 | 4.12 | -�� |
| �g�ѐ� |
4.45 | 4.25 | -�� |
| �@�\�� |
4.75 | 4.39 | -�� |
| �t�� |
4.63 | 4.30 | -�� |
| �z�[���h�� |
4.68 | 4.41 | -�� |
- ���v�����r���[�E���j�^�[���r���[�͏W�v�Ώۂ��珜�O���Ă��܂�
- ���u�J�e�S�����ρv���u���[���ρv���������ڂ����F�w�i�ɂ��Ă��܂�
| ���r���[�\�� |
|
|---|
�悭���e����J�e�S��
2015�N3��15�� 13:33 [806556-1]
| �����x | 5 |
|---|
| �f�U�C�� | 4 |
|---|---|
| �掿 | 3 |
| ���쐫 | 5 |
| �o�b�e���[ | 3 |
| �g�ѐ� | 5 |
| �@�\�� | 5 |
| �t�� | 5 |
| �z�[���h�� | 5 |
�J�~�钆�C�y�Ɏ��o����̂͐��\�̂ЂƂ��Ǝv�� |
12-50�L�b�g�����Y�ł����̃{�P��������̂͋��� |
2013�N����D800�ŃJ�����f�r���[�����B
36���K�s�N�Z���̈��|�I�Ȑ��ׂ��A�R���g���X�g�ƊK���̖L�����B�����ĕ����čw������50mmF1.4G�̑傫�ȃ{�P�ƂȂ߂炩�Ȏʂ�Ɋ��������B
�ǂ���70-200mmF2.8G���w���B�{�f�B�ƍ��킹��Ɩ�2.5�L���B�d�����f�J�C...�B���������͑�O���B50mm�P�Ŋ�����36���K�s�N�Z���̊�����傫���h��ւ��Ă��ꂽ�B
�����K���B�e�ɏo��悤�ɂ��āA�J�����ƃ����Y2�{�A�傫�ȎO�r��w�����Ă����B
�w�����@�A�Ƃ��������t����߂悤�ƍl���n�߂��̂��A�X���ŃX�i�b�v���B��悤�ɂȂ��������肩��B
���̑傫�������}�̂��A��ʑ̂����̐l�������ޏk�����Ă��܂��Ă���̂ɋC�Â�������B
�܂��A�����o���̂������ɂȂ�����A�B�e�ɍs���ړI�ł͂Ȃ����ɃJ������E���Ă��������Ȃ����肵���_�ł��Ƒւ����T�u�J������...�A�ƍl���Ă����B
�}�E���g�𑝂₷�̂͋��K�I�ɂ����S���傫���Ǝv��������A�@�ޏk����O���ɒu���A�~���[���X�����悤�ƌ��߂��B
����̂Ƀ�7�V���[�Y�͑I��������͂���A��6000��X-T1��E-M1�Ƃ���3���ɁB
�܂��\�j�[APS-C�̓����Y�����Ȃ��A�ʂ�ɐF�C���Ȃ����A�z�[���h�����ǂ����̂ł͂Ȃ������B
X-T1�͑��쐫�������Ί����������B
�t�W�̐F�͑�D�����������A�����Y�Q�����₩�Ȏʂ��������̂��������͓I�B�O���b�v���͏��������̂̍\���₷������Ă���Ɗ������B
�������ː��ɗ��Ɗ����������딯������Ȃ���p���B�e�wAF�ł��Ȃ��̂��ɂ������B
�����Ďc�����̂�E-M1�B
�����̃J�����ɂ��Ē��n�߂����������傤��40-150PRO���������ꂽ������ŁA�h���ꂩ��h�Ƃ��������������B���҂ł���A�ƁB
D800�ŃJ�����f�r���[�����̂������āA����̌n������ɋ߂����̂��ق����ƍl���Ă����̂ŁA�_�C������{�^���A�����Ă��̐ݒ�̏_��ɍ��ꂽ�B
�O���b�v�͂��̃{�f�B�T�C�Y�ɂ͂��傤�ǂ悭�z�[���h���Ă������肫���B
�����ʂ�Ɋւ��Ă̓C�}�C�`�Ȉ�ہB�Z���T�[�T�C�Y�ŕ�����������B�������������邱�Ƃ��ł���AAPS-C�Ɣ�r�ł��Ȃ����Ȃ����B
���t�H�[�}�b�g�����邱�ƂŎʂ肻�̑��ɂ͑Ë����邵���Ȃ��̂͂킩�肫���Ă����̂ŁA�h�ǂ��܂őË������ɍςނ��h�h�Ë��ł��Ȃ��_�͂ǂ����h���d�v�ł������B
�J�����{�f�B�ɂ͑��쐫�����҂����B���t���C�N�̂��̂��B���̓_��E-M1���w�����邱�Ƃɂ������ߎ�ł������ƍl���Ă���B
�����āA�e�}�E���g�ň�ʂ葵�������́A�V�X�e���S�̂ł̋��K�I���S�A�܂����ʓI���S�̏��Ȃ��������I���������R�̂ЂƂ��B
�ʂ�ɂ����ẮA���𑜓x�t���T�C�Y�Z���T�[���痣��鎞�_�ŁA���ɂ�����߂�������x���Ă����̂ł��܂�l���邱�Ƃ͂Ȃ������B
�����������̂ł͂Ȃ��A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Z���T�[�Ƃ��ď\�ɗǂ����̂Ɗ����Ă���B
�y�f�U�C���z
OM����𐏏��Ɋ���������N���V�J�����B
���������Ă��Ă�����ɗn�����ރt�����h���[�ȃV���o�[��I�B
AEL�{�^����AF�����蓖�ĂĂ��邪�A�O���b�v�����肱��ł���Ə��������C������B
������������Ă����Q�̑��쐫���߂��������������f�U�C���ɗ��Ƃ�����ł���B
�y�掿�z
�Z���T�[�T�C�Y�̓t���T�C�Y��4����1�Ƃ͎v���Ȃ��قǂ̃|�e���V����������B
�����ߋ����ł͂悭���Ȃ�����������Ȃ����x�����A���i�ł͗�R�Ƃ���B
���F�͎�Ђ����߂��B
�����x�ϐ��́A��r�ΏƂ��������A�t���T�C�Y�����ׂ���A�ЂƂ��܂���Ȃ��ア���̂��B
ISO-Auto��200�`1250�ɐݒ肵���B
�y���쐫�z
���Q���B���̉��i�тł���𗽂����̂͂Ȃ����낤�B
���܂Ŕ�h�o�h�H�d�l�̃J�������g���Ă����̂Ȃ�A������������{�^�����������Ƃ��̃t�B�[�h�o�b�N�Ɉ�a�����o���邩������Ȃ��B
������������ƒ�ł��������邩����͂Ȃ��B
�y�o�b�e���[�z
���肪�����A�[�d�Ɏ��Ԃ�������B
�~���[���X�����犄���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��납�B
�o�b�e���[�Q�[�W��3�i�K�Ƃ����̂��ɂ����B4�i�~���������B
�y�g�ѐ��z
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ��Ă͑傫�߂Ȃ��̋@����AD800�̔����ȉ��̎��ʁB
�y���̂ŋ�ɂȂ�Ȃ��B
�܂��A��������"�o�b�O�̒��ɔE���Ă���"���ł���B
�y�@�\���z
�h���\�h�ł͂Ȃ��h�@�\�h�ł���B
���܂�ɑ������Ċo������Ȃ��B�g����Ȃ��B
�t�H�[�T�[�Y���[�U�[�ł�PEN���[�U�[�ł������ł���悤������L���Ă���̂��낤��...�B
�Ȃ�ΐ���������������ƍ���ė~�����A�Ǝv�����B
�y�t���z
�Y�킾�B����ȏ�̍��𑜓x���͂���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
D800�̓��C�u�r���[�ł̎B�e�A���Ɋg�債�Ă�MF�ɓ�(�h�b�g�o�C�h�b�g�܂Ŋg��ł��Ȃ�)���������̂ŁA�������Ă���B
�F���x�Ɩ��x�̐ݒ肪�ł���B
�y�z�[���h���z
��q�̒ʂ�A�O���b�v���悭�o���Ă��ăz�[���h���₷���B
�����A����a�����Y��t�������ɁA�O���b�v�ƃ����Y�̃N���A�����X�ɕs���������邩������Ȃ����A�����ȃ{�f�B�Ƃ̃g���[�h�I�t���B
�܂��A�T���O���b�v���Ȃ��炩�����đ���Ă��Ȃ��B
E-M10�܂łƂ͍s���Ȃ��Ă��A���������N���̂���T���O���b�v�ł��ǂ������̂ł͂Ȃ����B
�y���]�z
���@���̂Ƃ���AD800��"���ė]���Ă���"�B
�����炱���A�g�̏�ɂ������J�����Ŋy���݂��������B
E-M1�Ȃ珉�S�҂ł����܂��t�������邾�낤�J�������Ɗ������B
���͂܂�RAW�ł����B�e���Ă��Ȃ����A�A�[�g�t�B���^�[�ȂǂŗV��ł݂�̂������������ɂȂ邩������Ȃ��B
����E-M1�́h�{�C�h�ɂ��Ȃ�邵�A�h�V�сh�����i�ł���ł��낤�A�ƂĂ����������J�������B
- ��r���i
- �j�R�� > D800 �{�f�B
- �I�����p�X > OLYMPUS OM-D E-M10 �{�f�B
- ���x��
- �A�}�`���A
- ��Ȕ�ʑ�
- ���i
- ��i
- ����
- ���̑�
�Q�l�ɂȂ���28�l
���̃��r���[�͎Q�l�ɂȂ�܂������H![]()
�悭���e����J�e�S��
![]() 2014�N3��18�� 21:15 [652847-5]
2014�N3��18�� 21:15 [652847-5]
| �����x | 5 |
|---|
| �f�U�C�� | 5 |
|---|---|
| �掿 | 4 |
| ���쐫 | 4 |
| �o�b�e���[ | 2 |
| �g�ѐ� | 4 |
| �@�\�� | 5 |
| �t�� | 5 |
| �z�[���h�� | 5 |
�L���m���̂T�c�}�[�N�V�����C���Ŏg���Ă���̂ŁA���X��r�ŏo�Ă��܂��B
���d�r���ۂ��Ȃ��B
�@�P�������ďo��ɂ͂T���炢�Ȃ��ƈ��S�ł��Ȃ��Ƃ�����ہB���͂S�����ďo�Ă��܂��B
�@�P������̎B�e�\�����͂Q�O�O�`�Q�T�O���Ƃ������Ƃ���B
�@�P�O�O�O���B��̂ɂR�ő����̂��H�Ƃ��������B�T�c�R�̏ꍇ�́A�펞�R�g�т��Ă��邪�A�P���ɂQ���g���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B
�@�݊��d�r���S�g�������A���łɂQ�͂��̐��s���B�����ł��������B��Ȃ��J�����Ȃ̂ŁA�d�r�̍����傫���o��悤�Ɏv����B���܂ł̃J�����Ō݊��d�r�Ɉ�����ۂ����������Ƃ͂��܂�Ȃ����A���̃J�����ł́A�B�e�\�������l����ƁA�����ł�������I��ł����ق�������Ǝv���B
�@���ƁA��ۂƂ��ẮA�ڐ����P�R�ɂȂ����Ǝv������A�X�g���Ɠd���������邱�Ƃ��悭����B���̂��߂ɃV���b�^�[�`�����X�������Ƃ���x�Ȃ炸����B����ł͈��S���Ďg���Ȃ��B�T�c�R�Ȃ�A�ڐ����P�ɂȂ��Ă���ł��A����ł����Ƃ������炢�����Ȃ��B
�i��̂U�s�A2014.3.18�NjL�j�B
�@�u����������Ԃ��I�t�v�ɐݒ肷��Ə����͂܂��ɂȂ�炵�����A�����Ƃ��Ă͂���Ȃɑ����銴�������Ȃ��B
���e�w�`�e�����������A�K���Ȉʒu�Ɋ��蓖�Ă���{�^�����Ȃ��B
�@info�{�^���̈ʒu���P�Ԃ������A���蓖�Ă��Ȃ��B�e���Q�Ɂu�`�d�k�^�`�e�k�v�����肠�Ăāu�l�����w�`�e�v�ɂ��邩�A�O�ʂ̃{�^���Ɋ��蓖�Ăāu���w�`�e�v�ɂ��邩�A�Ƃ������Ƃ���B�i�ݒ�̂������ɂ��Ă̓N�`�R�~�̋L�����u�e�w�`�e�v�Ō������ĎQ�l�ɂ��Ă��������j
���Đ��{�^���Ƃ��A���܂�o������Ȃ��悤�ɍ���Ă��邽�߂��A�閾���O�̎B�e�ȂLjÂ��Ƃ���ł͎w�̊��G�ňʒu���킩��Â炢�B�Đ��{�^���AAEL/AFL�{�^���A�����ĈӊO�Ȃ��ƂɃ��[�h��ւ����o�[�����A�ڂŊm�F���Ȃ��ƂȂ��Ȃ��w�ŒT��Ȃ��B������������B����F�ł������悭����Ă���̂��A�����ł͋w�ɂȂ��Ă��邩���B
���F�̐ݒ�́uvivid�v�����C�ɓ���B�����ݒ�ł͂������Ԃ銴��������̂ŁA�w�ʂ̃p�l����A+2 G-2�ɂ��Ă���B
��ISO800����p�ł��邩�Ƃ����Ƃ���B�������A1600�A3200���掿���}���Ɉ�������Ƃ��������ł͂Ȃ��B
�@�t�ɁA�ኴ�x����r�ꂪ�ڗ������B�T�c�R�̂ق��������ԗǂ��i���R�H�j�B�܂��A�����ɂ͔�ׂĂ��Ȃ����AISO1600�ȏ�Ƃ��̍����x�ł́A���̋@��̒��O�Ɏg���Ă����d�|�o�k�T���A�悢�C������B
���s���g�͒����Œ�A��F���̓I�t�ɐݒ肵�Ă��邪�A�s���g���͂������Ƃ�����B�T�c�R�̂ق������S�B
���w�ʂ̏\���{�^���i�Ƃ��ɍ��{�^���Ƃ����{�^���j�������ƁA�M���Ƃ��L�V�݂����ȉ����o��B
�@�Đ����Ƃ��A���{�^����A�����ĉ����Ƃ��ȂǃL�V�L�V�������Đ��_�I�ɂ͕s���B���ł������Β���̂��H�i�ł��A����Ă݂�̂͂�����Ƌ��낵���@���@���܂ł��C���������̂ŁA�j�t�q�d�T�T�U���V���b�Ƃ�����Ⴂ�܂����i���{�^���Ɖ��{�^���j�@���M���M�������~�܂�܂����B�@�����߂܂���B��肽���l�͎��ȐӔC�ŁB�j
������̐ݒ�ł́A�A�ʂ�I�ԂƎ�Ԃ�������ɃI�t�ɂȂ�B�����͐������s�\���ŁA�d�l�����P���Ăق����Ƃ���B�ǂ����邩�Ƃ����ƁA���j���[�̉��̂ق��ŁA�u�w�A�ʎ���Ԃ����I�t�x���I�t�v�i���A�ʎ��ɂ���Ԃ����I�t�ɂ��Ȃ��j�Ƃ����ݒ�ɕς��Ȃ��Ă͂����Ȃ��i�킩��ɂ��[�j�B���߂āA�A�ʂ�I�ԂƁA��Ԃ��̍��ڂ��O���[�ɂȂ�Ƃ��ɂ��Ăق����B�i2014.3.18�A���̍��ڈꕔ���������j
���{�̂��������������Ǝv�����A�_��ɂ���Ă͓d�r�Ԃ��Ɗ����āA�_����͂���������߂��肵�Ȃ��ƁA�ӂ����J���Ȃ��B���Ƃ��Δ~�{���쏊�̎��R�^��ł͂r�k�|�S�O�y�r�b�i���T�C�Y�j�͌Œ肵���܂܁A�d�r�̏o�����ꂪ�ł��邪�A�r�k�|�T�O�y�r�b�i���T�C�Y�j�ɂȂ�ƁA�Œ肵���܂܂ł͓d�r�������ł��Ȃ��B
���]�@�@�{�^���ނ������A�J�X�^�}�C�Y�ł��鍀�ڂ������̂͂��肪�����B�f�U�C�����@�\����������l�܂��Ă��銴�����\��Ă��ă}�j�A�b�N�Ȋ����B�~���[���X�̒��ł͑傫�����ނƂ͂����Ă���͂���t�ɔ�ׂ�Δ��ɏ������A�����Y���܂߂��̐ςƂ��Ă͔��ɏ��������܂肠�肪�����B
�������Ƃ��菑���Ă��������Ȃ��̂ōׂ��Ȃ��Ƃ����낢�돑���܂������A�d�r�������Ȃ����ƈȊO�͊y�����A�����J�����ł��B
- ��r���i
- CANON > EOS 5D Mark III �{�f�B
- ���x��
- �A�}�`���A
- ��Ȕ�ʑ�
- ���i
- ��i
�Q�l�ɂȂ���38�l�i�ă��r���[��F16�l�j
���̃��r���[�͎Q�l�ɂȂ�܂������H![]()
�悭���e����J�e�S��
2013�N10��15�� 20:39 [640125-1]
| �����x | 5 |
|---|
| �f�U�C�� | 5 |
|---|---|
| �掿 | 5 |
| ���쐫 | 5 |
| �o�b�e���[ | 5 |
| �g�ѐ� | 4 |
| �@�\�� | 5 |
| �t�� | 5 |
| �z�[���h�� | 5 |
��^�O���b�v���t�����t���O�V�b�v�炵���������̂���{�f�B |
����Ƀm�C�Y�����y�����ꂽ�����x�`�ʗ́iISO3200�j |
�L��16���K��f�����������𑜗� |
���삪�L�����F���������d�q�r���[�t�@�C���_�[ |
�g���O�����̃��b�N�@�\���������[�h�_�C���� |
����p�̍L���`���g���Ή��̉t�����j�^�[ |
�y���]�z
�@�I�����p�X���f�W�^�����t���玖����P�ނ��邱�Ƃ͎c�O�ł����AE-M1�̓I�[�g�t�H�[�J�X���\��V���b�^�[�̃L���ȂǁA�t���O�V�b�v�@�ɒp���Ȃ����͓I�ȃJ�����Ɏd�オ���Ă��܂��B�{�f�B�̃R���p�N�g����A�t���O�V�b�v�@�Ƃ��Ă͈����Ȏ������i�́A�~���[���X�J���������炱�������ł����̂�������܂���B������ۂɎg���Ă݂āA�����g�����Ƃ��o����J�������Ǝv���܂����B
�y�f�U�C���z
�@�ꌩ���āu�I�����p�X�̃J�����v�Ƃ킩��f�U�C���ł����AE-M5�ƕ��ׂĂ݂�ƕς�����_�����Ȃ�����܂���B�\�ʂɓ\�t����Ă���S���̃p�^�[�������ڊv���ɂȂ�ȂǁA�S�̂ɍ������������Ă���Ǝv���܂��B�I�����p�X�E�����Y�������J�����̃t���O�V�b�v�@�Ƃ��Ăӂ��킵���f�U�C�����Ɗ����܂����B
�y�掿�z
�@�C���[�W�Z���T�[���V����̂��̂ƂȂ�܂����B�L����f���͓����ł����A�Ƃ��ɍ����x�ł̕`�ʐ��\�����サ�Ă���Ǝv���܂��B�m�C�Y�����ɔ����Ĕ����������ƂȂ�𑜊��̒ቺ���AE-M5��E-P5�����}�����Ă��܂����B
�i�P�j�����x���\
�@E-M5�Ɣ�ׂ�ƑS�̂Ƀm�C�Y�����y������Ă��܂����A�Ƃ���ISO3200�ȏ�ňႢ�������܂����B�����x�m�C�Y���_�N�V������W���ɂ��Ă����ƁA��ʓI�ȎB�e�ł����ISO3200�ł���p��Ƃ��Ċ��p�ł���Ǝv���܂��B
�@�ݒ�ł��銴�x��ISO25600�܂łł��B���̃��x���ɂȂ�ƁA�������Ƀm�C�Y����𑜊��̒ቺ���C�ɂȂ�܂����A��̑O�ɂ悭����ꂽ�悤�Ȕj����͂��Ȃ����߁A�g�������H�v����Ί��p�ł��郌�x�����Ǝv���܂��B
�i�Q�j�𑜗�
�@�L��16���K��f�̂��߁A�𑜗͂̓_�ł��\���Ȏ��͂������Ă��܂��B���ۂ�ISO12233�`���[�g�Ńe�X�g�����Ƃ���A�قƂ�ǃ��A�����������Ƀe�X�g���E�ł���2500�{�̃��C�������ʂł��܂����B��������ߕ����̃e�X�g�p�^�[���ł��A��������Ɖ𑜂��Ă��܂����̂ŁA16���K��f�����������摜��������Ǝv���܂��B
�i�R�j�V�F�[�f�B���O�
�@E-M1�ɂ���ʎ��ӕ��̗������݂�����@�\�𓋍ڂ��Ă��܂��B�e�X�g�ɗp�����̂�14-42mmIIR�̃L�b�g�p�����Y�ł����A�L�p�[�i��J���Ŕ���������ӌ��ʕs�����y������܂��B�c�Ȏ�����Ɣ�ׂ�ƌ��ʂ͂킩�肸�炢��������܂��A��Ȃǂ̂悤�Ȗ��n�̔�ʑ̂��B�e����Ƃ��Ȃǂ͐ϋɓI�Ɋ��p�����Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�y���쐫�z
�@�t�����g�ƃ��A��2�_�C�����̋@�\�����o�[�Ő�ւ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�����Ƃ��Ȃ�g���₷����������Ǝv���܂��B����ȊO�ɂ��t�@���N�V�����{�^���Ȃǒ��ړI�ɑ���ł���{�^���ނ������ݒu����Ă��܂��B
�@�{�f�B�O�ʂɂ̓z���C�g�o�����X�������^�b�`�Őݒ�ł���{�^�����V�݂���Ă��܂��B�t�B�����J�������ォ�璲���Ȃǂɂ�������Ă����I�����p�X�炵���������܂��B
�y�o�b�e���[�z
�@E-M5�Ɠ����o�b�e���[�ł��B�d�l�ł�350���̎B�e���\�ƂȂ��Ă��܂����A���ۂɂ͔{�߂��̖������B�e�ł��܂����B���̕ӂ�͎B�e�X�^�C���ɂ���Ă��Ȃ荷���o�Ă��镔���ł����A�ł���Η\����p�ӂ����Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�y�g�ѐ��z
�@E-M5�Ɣ�ׂ�ƈ���傫���Ȃ�d����70g���x�����Ă��܂����A�t���O�V�b�v�E�J�����Ƃ��Ă͋ɂ߂ď��^�y�ʂȃJ�����ł��B�t�����Ă���X�g���b�v�͐�p�i�ŁA�@�햼�̕������h�J�ƂȂ��Ă���ȂǁA��������Ƃ������ł��B
�y�@�\���z
�i�P�j�I�[�g�t�H�[�J�X
�@E-M5�Ɣ�ז��炩�ɍ���������A�������Ƃ����Ȃ��Ȃ������Ƃ��������܂����B����̓t�H�[�T�[�Y�p�̃����Y�̓e�X�g�ł��܂���ł������A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�p�����Y�ɏ������I�[�g�t�H�[�J�X���\�����������悤�ł��B
�i�Q�j�d�q�r���[�t�@�C���_�[
�@�\����������傫���Ȃ�A����������Ă��܂��BE-M5�ł����₷�������ł����A����ɐi���������Ƃ��������܂����B�\���̒ǐ������ǂ��A�摜�̒x����������͂قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�i�R�jWi-Fi
�@�B�e�f�[�^�̉{����]�������łȂ��A�X�}�[�g�t�H�����ł̃����[�g����ɂ��Ή����Ă��܂��B
�i�S�j�A�ʐ��\
�@E-M5��E-5�����啝�ɋ������ꂽ�̂��A�A�ʐ��\�E�A���B�e�����ł��B
�@�����ȃJ�[�h��p����ƁA��ԃf�[�^�ʂ�����RAW+JPEG�iFine Large�j�ł�47�R�}�̘A�ʂ��\�ł����B�o�b�t�@�[����t�ɂȂ�������A�T��2.1�R�}/�b�̃y�[�X�ŃJ�[�h�e�ʈ�t�܂ŎB�e�ł��܂��BJPEG�iFine Large�j�ł���A�T��7.6�R�}/�b�̃y�[�X�ŃJ�[�h�e�ʈ�t�܂ł̖����A�ʂ��\�ł��B�ԈႢ�Ȃ��A�g�b�v���x���̘A�ʐ��\�E�A���B�e�������Ǝv���܂��B
�y�t���z
�@E-M5��������������܂����B����p���L�����F�����ǍD�ł��B�Ȃ��A�I�����p�X�̃~���[���X�J�����ł̓A�X�y�N�g��3:2�̉t���p�l�����̗p����Ă��܂��B����B�e���Ȃǂ��l���Ă���̂��Ǝv���܂����A��͂�C���[�W�Z���T�[�Ɠ����A�X�y�N�g��̉t���p�l���̕����A���傫�ȐÎ~�摜��\���ł��܂��̂ōD�܂����Ǝv���܂��B
�y�z�[���h���z
�@��^�̃O���b�v���V�݂��ꂽ���߁A�����ڈȏ�Ƀz�[���h���͗ǍD�ł��B�d�q�r���[�t�@�C���_�[�ڊᕔ�����p���邱�ƂŁA���Ȃ���肵���ێ����ł���Ɗ����܂����B
�t�L�F��L�ŋL�ڂ���ISO12233�`���[�g�⍂���x�e�X�g�̌��f�[�^���f�ڂ����T�C�g���쐬���܂����̂ŁA��낵������킹�Ă��Q�Ƃ��������B
http://www.monox.jp/digitalcamera-sp-olympus-omdem1.html
- ��r���i
- �I�����p�X > OLYMPUS OM-D E-M5 �����Y�L�b�g
- �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P5 17mm F1.8�����Y�L�b�g
�Q�l�ɂȂ���42�l
���̃��r���[�͎Q�l�ɂȂ�܂������H![]()
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����z����PC
-
�y�~�������̃��X�g�z�V�o�b2025
-
�yMy�R���N�V�����z�������30��PC
-
�y�~�������̃��X�g�z�v�����^�w��2025
-
�yMy�R���N�V�����z15���炵��
�i�f�W�^�����J�����j
- �R�~���j�e�B�K���̓��e�����m�F�̏�A�����p��������
- �]���͓��[���ꂽ���̎�ςɂ��ڈ��ł���A��ΓI�ȕ]����ۏ�����̂ł͂���܂���
- �_���̓��A���^�C���X�V�ł�
- ���[�U�[���r���[�̎g�����A�悭���鎿�� FAQ�����Q�Ƃ�������
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h